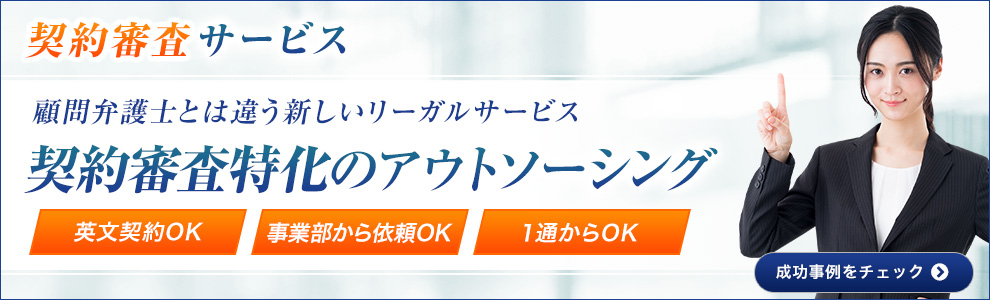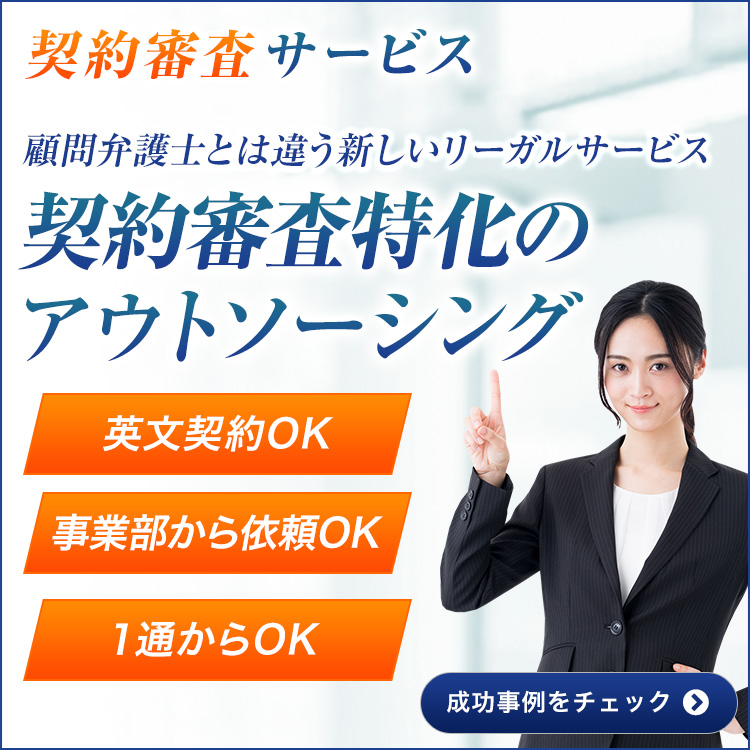- 2025.03.19
請負契約に関する民法改正のポイントと、解除の基本ルールを詳しく解説
請負契約とは仕事の完成を約束し、その報酬を受け取る契約形態で、多くのビジネスシーンで用いられています。しかし、契約違反などがあった場合、正しい手続きを踏まなければ大きなトラブルにつながりかねません。特に2020年4月の民法改正により、契約不適合責任や解除の条件、手続きに関する規定が大きく変わりました。
この記事では、民法改正のポイントも踏まえつつ、「請負契約」「契約解除の基本ルール」について概説し、なかでも請負契約の典型的な例である「工事請負契約」の解除のルールについて解説します。
目次
請負契約とは
請負契約の基本的な特徴
請負契約について、民法に以下のとおり定められています。
「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」(民法第632条)
請負契約とは、請負人(仕事を請け負う側)が特定の仕事を完成させることを目的とする契約であり、たとえば、建築工事やリフォーム工事、システム開発にかかる契約等がこれに該当します。請負人は、契約で取り決めた仕事を完成させる義務を負い、注文者(仕事を依頼する側)はその報酬を支払う義務があります。
請負契約と混同されやすい契約として、委任契約(準委任契約)が挙げられますが、委任契約(準委任契約)では“業務の遂行自体を目的とする”(準委任契約の例:コンサルタントにコンサルティングを依頼する場合。コンサルティングそのものが目的。)のに対し、請負契約ではあくまでも“仕事の完成が目的”(請負契約の例:建築会社にビルの建築を依頼する場合。ビルの完成が目的。)であるという点がその特徴であり、重要なポイントとなります。
上記の特徴から、請負契約では、特に契約当事者間の意思の合致が重要であり、目的である仕事の完成について明確に定めた詳細な仕様書や契約書の作成が必要になります。これにより、後々のトラブルを未然に防ぐことができ、契約解除の際にもスムーズな手続きが期待できます。
| ▶参考情報:請負契約と委任契約については下記の記事でも解説していますので、ご参照ください。 ・委任契約と請負契約の違いとは?業務委託契約において業務範囲を示すうえでの注意点|委託者側の契約審査(契約書レビュー)Q&A |
請負契約に関する民法改正のポイント
瑕疵(かし)担保責任から契約不適合責任へ
2020年4月に施行された民法改正では契約不適合責任という新しい概念が導入され、旧民法の瑕疵担保責任と置き換えられました。改正民法第562条から第564条は、売買契約における契約不適合責任を定めています。契約不適合責任とは、買主が、契約に基づいて提供される成果物が契約上の仕様や品質に適合していないことを発見した場合に、売主が負う責任のことです。買主は、売主に対して、目的物の修補や、代金減額等を請求することができます。
契約不適合責任は、売買契約以外の有償契約についても準用されることから(第559条)、請負契約にも準用され、売主=請負人、買主=注文者と読み替えることができます。
具体的には、民法改正後の請負契約では、完成した仕事が契約内容に適合しない場合(=契約不適合)、注文者は請負人に対して履行の追完(目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡し)(第562条)、代金の減額(第563条)、損害賠償や契約解除(第564条)の請求が可能となることが明確に定められました。また、契約不適合責任を追及できる期間制限についても改正されています。
契約が中途で終了した場合の報酬について
請負契約は仕事の完成を目的とする契約です。 それでは、仕事が途中で完成できなくなったり、仕事の完成前に契約が解除されたりした場合、注文者に責任がない場合でも、注文者は、請負代金を支払わなければならないのでしょうか。
旧民法ではこの点について明文化されていませんでしたが、2020年の改正により、請負人が既にした仕事のうち可分な部分の給付により注文者が利益を受ける場合は、その部分を仕事の完成とみなすこととされ、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができるようになりました(第634条)。
契約解除について
請負契約の解除のルールについても改正されています。具体的には、改正前には契約目的を達成することができない場合のみ契約解除が可能でしたが、改正により、契約内容の不適合が軽微なものでない場合には、契約目的を達成することができる場合でも、契約解除が可能となりました。
その他、後述しますが、注文者が破産手続開始決定を受けた場合の契約解除についても改正されています。
このように、2020年の民法改正により、請負契約にも大きな影響があります。2020年4月以前に締結した契約書や、企業内で使用している契約書の雛型における条項の見直しをまだ行っていない場合は、すみやかに見直す必要があるでしょう。さらに契約書の適用指針や各種ポイントについても理解を深めることで、契約解除の際のトラブルを防ぐことができます。
改正民法対応!契約解除の基本ルール
契約解除とは?
契約の解除とは、契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するとき、相手方への意思表示によって、契約の効力をさかのぼって消滅させることをいいます(民法第540条、第545条)。契約解除のルールは請負契約に限らず、すべての契約類型に共通するものです。
上記のとおり、解除の発生原因により2種類の解除があり、①法律の規定による解除は法定解除、②契約の規定による解除は約定解除と呼ばれています。また、法律の規定や契約によって発生する解除権によらず、当事者の合意によって解除することも可能であり、その場合は合意解除と呼びます。
①法定解除:
法定解除のひとつに、債務不履行による解除が挙げられます。契約当事者の一方が債務を履行しない(債務不履行といいます)場合、契約の相手方は契約を解除することができます(第541条、第542条)。
債務不履行は、履行遅滞や履行不能、不完全履行などに分類されます。履行遅滞とは、契約の履行が約定の期限を過ぎても行われないことを指し、履行不能とは債務の履行ができないこと、不完全履行とは、債務の履行はあったものの、履行内容が不完全な場合を意味します。なお先述の、民法改正により導入された契約不適合責任は、債務不履行責任の一種と解され、契約不適合があった場合には債務不履行の規定(第541条、第542条)が適用されます(第564条)。つまり、契約不適合があった場合、契約解除の理由となり得るということです。
②約定解除:
法定解除とは別に、当事者間で一定の解除発生事由を定め、その事由が認められた場合に契約を解除することができます。例えば、相手方が支払不能となった場合や重大な契約違反があった場合などを、契約書に解除事由として定めておく場合が挙げられます。
催告解除と無催告解除
契約解除はまた、解除の際の「催告」(裁判外で、債務を履行するよう求めること)の必要の有無により、①催告解除と②無催告解除に分類することができます。
①催告解除:(第541条)
まず契約の相手方に対して履行の催告を行い、合理的な期間を指定する必要があり、これを「相当の期間」と呼びます。この相当の期間を過ぎても履行されない場合に、契約解除が可能になります。なお、催告は口頭や普通郵便ではなく、内容証明郵便を利用するのが望ましいです。相手方から「催告は受けていない」と反論されることを防ぐことができますし、正しい手続きを踏んで解除したことを証明することができます。
②無催告解除:(第542条)
2020年の民法改正により、以下のように要件が詳細に定められました。
(ア) 債務の全部の履行が不能となったとき
(イ) 相手方が債務全部を履行拒絶したとき
(ウ) 債務の一部が履行不能又は相手方が債務の一部の履行を拒絶している場合に、契約の残存部分で契約の目的を達することができないとき
(エ) 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、相手方が履行をせずにその時期を経過したとき
(オ) 相手方が債務の履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
請負契約では、これら民法に定められた解除のルールと手続きについて理解し、契約において適切な条項を定めておくことは、契約当事者双方にとって重要です。契約を締結する際は、民法の定めより自社に不利でないか、実際の取引内容に照らし適切な契約不適合責任条項や解除条項となっているか、よく確認しましょう。また、万一解除が必要となったり、相手方から解除を請求された場合には、解除の正当性が問われる場合等もあるため、専門家のアドバイスを受けながら進めることが推奨されます。契約不適合責任や契約解除に関する知識をしっかりと把握し、適切な対応を心掛けましょう。
契約解除のルールと手続き~工事請負契約の場合
工事請負契約は、施工業者(請負人)が建物の新築・増改築などの工事を完成することを約束し、これに対し施主(注文者)が報酬を支払う合意がなされるという、請負契約の典型例です。工事請負契約を例にとりながら、解除のルールと手続きについて、施主(注文者)側からの解除と施工業者(請負人)側からの解除の場合に分けて見ていきましょう。
施主(注文者)側からの解除
工事請負契約において、施主側からの解除には、主に①施工業者の債務不履行(契約違反)に基づく解除(民法第541条、第542条)、②施主(注文者)都合による解除(第641条)の2種類があります。また、施主が施工業者に支払った手付金を放棄することで契約解除を行う手付解除(第557条第1項、第559条)という方法もあります。
①債務不履行に基づく解除:
上述した2020年4月の民法改正に対応して、施行業者に債務不履行(契約違反)があった場合の施主側による契約解除の手続きはより明確になりました。民法改正前は、“建物”に不具合があったとしても、契約解除は認められていませんでしたが、改正により当該規定は削除されました。
施主に損害が発生している場合は、施工業者に対する損害賠償請求が可能です(民法第415条)。例えば、施工業者が引き渡した建物に不具合があり、施主が他の施工業者に不具合を修補させた場合にかかった費用については損害賠償請求ができます。
また、施工業者の責任による解除であっても、完成部分の割合に応じた報酬の支払いが必要であることに注意が必要です(第634条)。例えば、施主が、工事の完成時期が遅れたことを理由に契約を解除した場合、解除までに完成した割合に応じて代金を支払う必要があります。
なお、引き渡し後に施行の不具合を理由に契約解除する場合は、「契約不適合責任」の問題となります。施主が不具合を知ったときから1年以内に施工業者に通知することが必要です(第637条)。
②施主(発注者)都合による解除:
施工業者が仕事を完成しない間は、施主は自分の都合で契約を解除することができます(第641条)。ただし、完成部分の割合に応じた報酬の支払義務を負うことに加え、契約解除により施工業者に生じた損害を賠償しなければなりません。損害の範囲には、契約を解除されなければ施工業者が得られたはずの利益(逸失利益と呼びます)も含まれるとされており、施工業者から高額な損害賠償請求を受けるリスクがあるため、注意が必要です。
施工業者(請負人)側からの解除
施工業者側からの解除については、施主側からの解除では認められているような、自分の都合による解除は認められず、例えば、施主が支払期日を過ぎても請負代金を払わない、施主が工事に必要な図面や資料を提供してくれないなど、施主の債務不履行に基づく解除、又は、施主が破産した場合などに限られます。ただし、2020年の民法改正により、仕事の完成後は、施主の破産を理由に、施工業者は請負契約を解除することはできない旨が定められました(第642条)。
違約金の有無とその計算方法
工事請負契約の解除に際しては、違約金の有無やその計算方法も重要な要素です。契約書に違約金に関する条項が明記されている場合、違約金の額については、契約書に記載された計算方法に基づき算出されます。
一般的には、請負契約の解除日までに行われた工事の進捗に応じた費用や、それまでに支出された労務費、材料費、その他の諸費用が違約金として計算されます。そのため、施主は契約解除を行う前に、施行業者としっかり話し合いを持ち、違約金の額について合意しておくことが望ましいでしょう。また、施工業者の立場からは、損害賠償額の上限が設定されている場合、それを超える損害が発生していても、施主に対して超過分を請求できない可能性があることにも注意が必要です。
違約金に関するトラブルを避けるためには、契約書作成時に違約金の有無や計算方法を具体的に明記しておくことも重要です。
| ▶参考情報:工事請負契約については下記の記事でも解説していますので、ご参照ください。 ・工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説! |
請負契約解除のまとめ
今回は、請負契約解除の基本ルールと手続きについて解説しました。請負契約の基本的な特徴から、2020年民法改正による留意点、契約解除の条件やその手続きについて詳しく説明しましたが、例えば注文者からの解除であっても、請負人の債務不履行に基づく解除なのか、または発注者の都合による解除なのかで、その手続きや効果が大きく変わってくるなど、様々なルールがありますので注意が必要です。
また、工事請負契約における契約解除後には、施主と施工業者の双方が合意する解決策を模索し、別の業者に工事を依頼する場合等でも、解除の影響を最小限に抑えて次のステップへ進むことができるよう対策を講じることが重要です。複雑な契約解除の手続きや、解除後のフォローについては、専門家に相談することで、トラブルを防ぎ、効率的に進めることができるでしょう。

-
弁護士 小野 智博弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士。
慶應義塾大学環境情報学部、青山学院大学法科大学院卒業。企業法務、国際取引、知的財産権、訴訟に関する豊富な実務経験を持つ。日本及び海外の企業を代理して商取引に関する法務サービスを提供している。2008年に弁護士としてユアサハラ法律特許事務所に入所。2012年に米国カリフォルニア州に赴任し、 Yorozu Law Group (San Francisco) 及び Makman and Matz LLP (San Mateo) にて、米国に進出する日本企業へのリーガルサービスを専門として経験を積む。
2014年に帰国。カリフォルニアで得た経験を活かし、日本企業の海外展開支援に本格的に取り組む。2017年に米国カリフォルニア州法人TandemSprint, Inc.の代表取締役に就任し、米国への進出支援を事業化する。2018年に弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所を開設。世界市場で戦う日本企業をビジネスと法律の両面でサポートしている。
-
 採用の際は要注意!雇用契約書で企業が注意すべきポイントとは
事業を行うにあたり従業員を雇用する場合、各従業員と使用者は雇用契約を締結することになります。
雇用契約書の基本知識や雇用契約書と労働条件通知書の違い...
採用の際は要注意!雇用契約書で企業が注意すべきポイントとは
事業を行うにあたり従業員を雇用する場合、各従業員と使用者は雇用契約を締結することになります。
雇用契約書の基本知識や雇用契約書と労働条件通知書の違い...
-
 契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
企業が取引を行う際には、必ず契約書を作成すべきです。
ただしネットなどで出回っている「雛形」「テンプレート」をそのまま使うとリスクが高いので、記名押...
契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
企業が取引を行う際には、必ず契約書を作成すべきです。
ただしネットなどで出回っている「雛形」「テンプレート」をそのまま使うとリスクが高いので、記名押...
-
 賃貸借契約内容に含むべき項目は?書き方のポイントとチェックの重要性
建物や土地、機械などの物を賃貸する場合「賃貸借契約書」を作成しましょう。
契約書がないと有効にならない賃貸借契約もありますし、そうでないケースでも書...
賃貸借契約内容に含むべき項目は?書き方のポイントとチェックの重要性
建物や土地、機械などの物を賃貸する場合「賃貸借契約書」を作成しましょう。
契約書がないと有効にならない賃貸借契約もありますし、そうでないケースでも書...
-
 労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
今回は労働契約と業務委託契約の違いに着目し、特に業務委託契約書に記載すべき重要ポイントを意識しながら、作成時に気を付けておくべき事を解説します。
労...
労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
今回は労働契約と業務委託契約の違いに着目し、特に業務委託契約書に記載すべき重要ポイントを意識しながら、作成時に気を付けておくべき事を解説します。
労...