
- 2024.01.04
普通建物賃貸借契約の賃借⼈から賃料(家賃・テナント料)の減額請求があったらどうすればいい?|賃貸⼈側の契約審査(契約書レビュー)Q&A
この記事では、「普通建物賃貸借契約において、賃借人からの賃料の減額請求があった場合に、賃貸人は必ず減額に応じなければならないのか?」について、賃貸人側からのご相談にお答えします。
目次
相談事例
~A社(普通建物賃貸借契約 賃貸人側)より~
4階建のオフィスビルを所有している当社(A社)は、現在使用していない当該オフィスビルの4階部分を賃貸に出し、テナントの募集を開始しました。
早速、賃貸事務所を探していたB社から申し込みが入り、物件(当社所有4階建オフィスビル)を内見したところ、B社は当該物件を大変気に入ってくださり、当社としても申し分のない相手方であったため、当社(A社)を賃貸人、相手方(B社)を賃借人とする、普通建物賃貸借契約を結ぶことにしました。
建物の賃貸借契約では、入居中や退去時などトラブルになるケースがあるとよく耳にします。ですので、今回賃貸人である当社(A社)から賃借人(B社)へ提案する契約書は、万が一を想定した内容でトラブルに備えたいと考えています。
そこで、一般的に賃貸物件でトラブルになるケースが多い場面を想定したとき、もし今回の普通建物賃貸借契約中に、賃借人(B社)から賃料の減額請求があった場合、賃貸人である当社(A社)は、必ずそれに応じなければならないのでしょうか? また、どのような点に注意して契約条項を定めたらよいでしょうか?
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所の回答
普通建物賃貸借契約において、賃借人から賃貸人に対し賃料の減額請求があった場合、賃貸人は必ずしも減額に応じる必要はありません。しかし、賃借人がどういった理由で賃料の減額請求をしているのかによって判断が分かれるため注意が必要です。
賃料をめぐるトラブルが発生するリスクを下げるため、契約にあたって、賃料減額請求について一定のルールを設けておくことが推奨されます。
以下、詳しく見ていきましょう。
まずは、「普通建物賃貸借契約」「賃料の減額請求」について、説明します。
普通建物賃貸借契約とは
まず、「賃貸借契約」とは、賃貸人が、ある物を賃借人に使用収益させ、これに対して賃借人が使用収益の対価(賃料)を支払うことを約束する契約です。(民法601条)
そして、「普通建物賃貸借契約」とは、その目的物を建物とする賃貸借契約です。
ここでいう建物に該当するか否かの判断は、構造上の独立性と、使用上の独立性によって判断されますが、いわゆる事業で使用するオフィスビルや、居住するためのマンションは、基本的にこの建物に該当するケースが多いです。
また、一般的には、賃貸借契約期間が1年以上(1年未満は期間の定めのないものとみなされます。借地借家法29条)で、原則として契約の更新があるという点が特徴になります。(一方、契約期間が満了すると契約の更新はなく、確定的に契約が終了するものは、定期建物賃貸借契約といいます。)
賃貸人、賃借人ともに更新しない旨の通知や解約の申し入れがない場合には、契約は同条件(条件を変更することも可能です。)にて更新されるため(借地借家法26条、27条)、再契約の手続きが不要など負担軽減につながります。
反面、賃貸人から契約を終了させたい場合には、「正当な事由」が必要となります(借地借家法28条)。一般的に、この正当な事由にあたるかどうかは賃貸人とってハードルになることが多いため、賃貸借契約を長く存続させたくない場合などは注意が必要です。
普通建物賃貸借契約を結ぶ上で関連する法律は、
民法、借地借家法、消費者契約法(賃借人が個人の場合)が考えられます。
本事例における契約関係
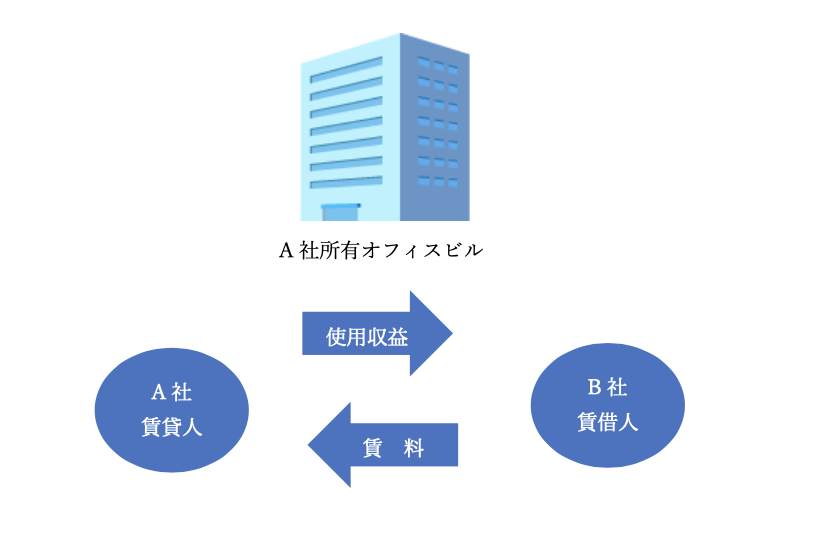
本事例においては、賃貸人であるA社からの相談になりますので、賃貸人側の目線において、また、賃借人B社は法人であるため、民法及び借地借家法の規定を中心として賃料の減額請求について見ていきます。
賃料の減額請求とは
賃借人は賃貸人に対し、賃料を支払う義務があります。(民法601条)
「賃料の減額請求」とは、賃借人から賃貸人に対して、経済事情等の一定の事情の変化により賃料が不相当となったとき、契約条件にかかわらず、将来に向かって建物の賃料の減額を求める請求です。建物における賃料減額請求権は、借地借家法32条に定められています。
逆に、同条において、賃貸人から賃借人に対して、賃料の増額を求める請求も認められています。
この賃料の減額請求と賃料の増額請求を合わせて、賃料の増減額請求といいます。
本事例の解説
「賃料の減額請求」について契約で定める必要性
賃貸人としては、賃料収入の減少はできるだけ回避したいところです。そうであれば、そもそも賃料の減額請求はできないという内容の、賃料不減額特約を契約で定めておけば良いのではないか?と考えるかもしれません。
しかし、普通建物賃貸借契約において、この賃料不減額特約を定めたとしても、原則それは無効になってしまいます(賃料不減額特約については、借地借家法上明確な規定はありませんが、判例などにより、賃料減額請求権を定めた同法32条1項は強行規定と解され、当該特約は無効となると理解されています)。したがって、賃借人B社からの賃料減額請求を禁じることはできないということになります。
では、賃料については何も定めをしない方が良いのかというと、そのような事はありません。
万が一トラブルになった際も、契約内容に定めがあるかどうかで、その後の方向性は大きく変わってきます。
ここで気を付けなければならないのは、賃貸人から賃借人に対する賃料の増額をしないという、賃料不増額特約は有効であるという点です。
この特約を定めてしまうと、賃貸人にとって原則一定期間は賃料の増額請求ができないことになってしまうので、リスクになることが考えられます。
今回のケースですと、賃料の改定について、賃貸人・賃借人双方がどのような場面でお互いに賃料減額、増額の請求ができるのかという内容を、明確に定めておくことが適切です。
「賃料減額請求に応じる可能性」のある場面
前述のとおり、賃借人からの賃料の減額請求をできないようにする特約(条項)は原則無効になってしまいます。そこで、どのような場合に賃料の減額請求に応じる可能性がでてくるのか、賃貸人としてはしっかりと把握したうえで、契約に定めておきましょう。
借地借家法において、賃料減額請求が認められる場面としては、以下の3つが挙げられます。(借地借家法32条)
①土地若しくは建物に対する租税その他の負担の減少
(たとえば固定資産税が大きく下がった場合など。)
②土地若しくは建物の価格の低下その他の経済事情の変動
(たとえばオフィスビルが古くなり価格が下がった場合など。)
③近傍同種の建物の賃料と比較して不相当となったとき
(たとえばその地域全体の賃料相場の水準が下がった場合など。)
このように、賃料の減額請求をすることができる法律上の要件を把握したうえで、実際にどういった場合に賃料減額請求を認めるのかを契約書に明記しておくことで、賃借人が賃料減額請求をしてくる可能性を限定し、賃料減額をめぐって賃借人とトラブルとなるリスクを下げることが期待できます。
また、上記はあくまで賃料の減額請求をすることができる要件であって、これらに該当するとして、賃料減額請求されたからといって、一律に必ずその請求に応じなければならないという訳ではありません。賃料の改定は、基本的には賃貸人・賃借人の合意に委ねられていますので、有効と判断されるであろう範囲内で特約条項を定めたうえで、賃料減額請求に対処していくことが望ましいです。
「不可抗力等による賃料の減額請求」改正民法
次に、賃貸物件である建物にトラブルが生じた場合の賃料の減額請求について見ていきましょう。
上述した通り、賃貸人は賃借人に対し、賃貸物件を使用収益させる義務を負っています。そして、賃借人は賃貸人に対し、賃料を支払う義務を負っています。
では、この賃貸物件が一部滅失してしまった場合、使用・収益できなくなってしまった場合はどうなるのでしょうか。
賃借人に帰責事由(責められるべき理由や落ち度など)がなく、賃貸物件が一部滅失してしまった場合、使用・収益できなくなってしまった場合、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額されることになります(民法611条)。賃借人に帰責事由がない場合とは、天災地変や自然災害など、不可抗力によるものが考えられます。
おわりに
以上のように、賃貸人は、普通建物賃貸借契約において、賃借人からの賃料の減額請求を想定したとき、どのような場合に賃料減額請求に応じる可能性がでてくるのかをしっかりと把握したうえで、それに備えた契約条項を考え、作成することが重要です。ただし、どんな契約でも自由に定めてよいわけではなく、また、実際に賃料減額請求がなされた場合も、その条項があるからといって一律に判断されるのではなく、いくつかの要素、基準を総合的に考慮して判断することになります。必要に応じて、弁護士等の法律専門家に確認を依頼しながら契約書作成や契約審査(契約書チェック・契約書レビュー)を行うことをお勧めします。
※本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。

-
弁護士 小野 智博弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士。
慶應義塾大学環境情報学部、青山学院大学法科大学院卒業。企業法務、国際取引、知的財産権、訴訟に関する豊富な実務経験を持つ。日本及び海外の企業を代理して商取引に関する法務サービスを提供している。2008年に弁護士としてユアサハラ法律特許事務所に入所。2012年に米国カリフォルニア州に赴任し、 Yorozu Law Group (San Francisco) 及び Makman and Matz LLP (San Mateo) にて、米国に進出する日本企業へのリーガルサービスを専門として経験を積む。
2014年に帰国。カリフォルニアで得た経験を活かし、日本企業の海外展開支援に本格的に取り組む。2017年に米国カリフォルニア州法人TandemSprint, Inc.の代表取締役に就任し、米国への進出支援を事業化する。2018年に弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所を開設。世界市場で戦う日本企業をビジネスと法律の両面でサポートしている。
-
 採用の際は要注意!雇用契約書で企業が注意すべきポイントとは
事業を行うにあたり従業員を雇用する場合、各従業員と使用者は雇用契約を締結することになります。
雇用契約書の基本知識や雇用契約書と労働条件通知書の違い...
採用の際は要注意!雇用契約書で企業が注意すべきポイントとは
事業を行うにあたり従業員を雇用する場合、各従業員と使用者は雇用契約を締結することになります。
雇用契約書の基本知識や雇用契約書と労働条件通知書の違い...
-
 契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
企業が取引を行う際には、必ず契約書を作成すべきです。
ただしネットなどで出回っている「雛形」「テンプレート」をそのまま使うとリスクが高いので、記名押...
契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
企業が取引を行う際には、必ず契約書を作成すべきです。
ただしネットなどで出回っている「雛形」「テンプレート」をそのまま使うとリスクが高いので、記名押...
-
 賃貸借契約内容に含むべき項目は?書き方のポイントとチェックの重要性
建物や土地、機械などの物を賃貸する場合「賃貸借契約書」を作成しましょう。
契約書がないと有効にならない賃貸借契約もありますし、そうでないケースでも書...
賃貸借契約内容に含むべき項目は?書き方のポイントとチェックの重要性
建物や土地、機械などの物を賃貸する場合「賃貸借契約書」を作成しましょう。
契約書がないと有効にならない賃貸借契約もありますし、そうでないケースでも書...
-
 労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
今回は労働契約と業務委託契約の違いに着目し、特に業務委託契約書に記載すべき重要ポイントを意識しながら、作成時に気を付けておくべき事を解説します。
労...
労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
今回は労働契約と業務委託契約の違いに着目し、特に業務委託契約書に記載すべき重要ポイントを意識しながら、作成時に気を付けておくべき事を解説します。
労...


