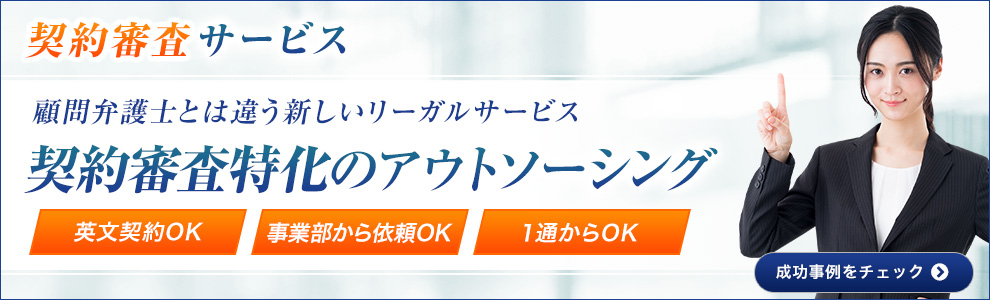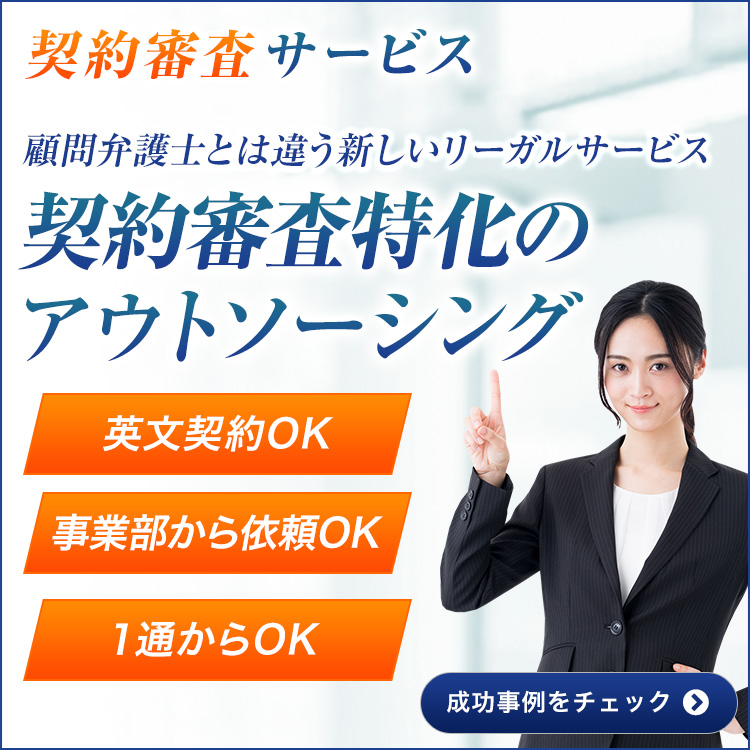- 2025.10.07
英文契約書のサインおよび日付の書き方や注意点とは?署名などのサンプル付きで解説
グローバル化が進む現代において、英文契約書は日本企業にとって欠かせない法的文書です。特にサインや日付の書き方は、契約の効力や当事者の責任を確定させる極めて重要な要素となります。たとえば、署名権限の有無や肩書の誤記、日付の記載方法を誤ることで、契約の有効性が争われたり、思わぬトラブルにつながることもあります。日本の契約実務とは異なり、欧米では印鑑文化がなく、署名や日付の扱いに独自の慣行があるため、正しい理解と運用が不可欠です。
この記事では、英文契約書におけるサインおよび日付の基本的なルールや注意点、署名欄や日付欄を含む英文契約書作成を弁護士に依頼するメリットについて、具体例とともに弁護士がわかりやすく解説します。
英語契約書のサインの書き方(種類)
英文契約書の署名欄に記載すべき4項目
英文契約書において、署名欄(signature block)は、契約の当事者が法的に同意したことを証明する極めて重要な部分です。一般的に記載を求められることの多い4項目は、以下のとおりです。
1. 会社名(Company Name)
例:ABC Corporation
2. 署名者の肩書(Title)
例:President、Director、Authorized Signatoryなど
3. 署名(Signature)
例:John Smith(手書き署名)
4. 名前の印字(Printed Name)
例:John Smith
たとえば、実際の署名欄は以下のようになります:
| ABC Corporation By: ___________________________ John Smith President |
※「By」の代わりに「Signature」や「Signed by」と表記される場合もありますが、同じ意味です。
ここで重要なのは、会社名が正式名称で記載されていること、役職が明記されていること、署名が本人によるものであること、そして印字された名前が併記されていることです。
なお、日本企業の担当者が署名する場合、「代表取締役社長」を英語で「President and Representative Director」などと訳すのが一般的です。役職表記は契約書における法的立場を示すため、正確さが求められます。
英文契約書でサインする場所
署名は、契約書の末尾に記載された「署名欄(signature block)」で行いますが、場合によっては契約書の各ページのフッター部分に「イニシャル(initial)」を記載するよう求められることもあります。これはページの改ざんを防ぐための措置で、以下のようなケースがあります。
- 契約が長文にわたる場合に各ページに署名者のイニシャルを書く
- 契約書の重要条項(例:損害賠償条項)に個別の確認としてイニシャル欄が設けられる
たとえば、フッター部分に「Initial: _______」と記載があれば、John Smithの場合、「JS」と手書きで記入する必要があります。
また、契約書が2部作成される場合、原本それぞれに署名するのが通例です。相手方の署名済みの原本を確認した上で署名するという流れになります。
英文契約書でサインする際の書き方
サイン(署名)の方法は、以下の点に注意が必要です。
- 必ずボールペンなど消えない筆記具で署名すること
- 名前のスペルを誤らないこと
- 肩書と名前は印字と手書きの両方で明記すること
- 複数の署名者がいる場合は、署名の順序も確認すること
たとえば、共同代表制の企業であれば、両名の署名が必要となるケースもあります。このような場合、契約書には以下のように署名欄が記載されることがあります。
|
ABC Corporation By: ___________________________ By: ___________________________ |
なお、法的には署名は漢字・ローマ字(アルファベット)どちらで記入することも可能ですが、相手方当事者が外国企業である場合、相手方へ配慮してローマ字(アルファベット)で記入する方がスムーズです。
また、デジタル署名が使用されるケースも増えていますが、電子署名が使用できるかどうかは契約の種類や該当する法域に依存します。たとえば、不動産の売買契約など一部の契約では、電子署名が無効とされる場合があります。秘密保持契約(NDA)では電子署名が広く使用されていますが、相手国の法制度や証拠能力の要件に照らして検討が必要です。
英文契約書の署名欄の例
以下は、署名欄の具体的なサンプルです:
|
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed this Agreement as of the date first written above. By: ___________________________ XYZ Inc. By: ___________________________ |
上記の例では、両当事者がそれぞれの会社を代表して署名しており、契約締結の意思が明確に示されています。署名欄には、「IN WITNESS WHEREOF~」のような形式的な前文(句)もよく使われます。これは「本契約の証として、本契約の締結日に、以下の者が署名する」という意味合いで、英語契約書では一般的な表現です。
英文契約書でサインは割り印・契印の代わりとなる
日本の契約書では、複数ページにまたがる契約の場合に、契印(ページ間の割り印)を用いることがありますが、英文契約書では日本のような契印や割り印の慣行は存在しません。代わりに、契約書の全ページにページ番号(例:Page 1 of 10)を記載したり、署名者のイニシャル(Initial)を各ページに記入したりすることで、改ざん防止の手段とします。
また、法人実印や代表印を用いる日本と異なり、欧米では手書きの署名のみで重要な書類や契約の有効性が認められるのが一般的です。これが、日本の商習慣と異なる点であり、印鑑の押印漏れによる無効のリスクは、英文契約書にはほぼ存在しません。
英語契約書の日付の書き方
英文契約書では「締結日」と「サイン日」を明示的に書き分けるのが一般的
英文契約書では、「契約締結日(Effective Date)」と「署名日(Date of Signature)」が異なるケースが多く見られます。これは、契約が法的に効力を持つ日と、実際に署名が行われた日が一致しない可能性があるためです。
たとえば、以下のような例が考えられます:
- 契約書が2025年4月1日付で作成されているが、実際の署名は4月5日
- 「This Agreement is effective as of April 1, 2025」と記載することで効力発生日を明示
このように、契約の効力が遡及する形になることがあります。この際には、契約条項に以下のような記述を入れることが一般的です。
| This Agreement shall be effective as of April 1, 2025, notwithstanding the date of execution. |
一方で、契約実務上は、署名日をもって効力発生とするケースもあります。たとえば、以下のように書かれる場合です。
| This Agreement shall come into force upon the date of the last signature hereto. |
この表現は「最後に署名された日をもって契約が発効する」とするもので、双方が署名を終えたタイミングで契約が有効になります。
英文契約実務における発展的注意点
近年はクロスボーダー取引が増えており、時差や営業日、祝日などを考慮し、意図的に「遡及日付(retroactive date)」を指定するケースもあります。特に国際M&A契約やライセンス契約では、監査の都合や規制当局への届出日程などの関係から、契約日と効力発生日がずれることが一般的です。
たとえば、「Effective as of April 1, 2025」とすることで、実際の締結が4月10日でも、4月1日から法的効力を持つことが可能になります。
ただし、税務・会計・監査の観点から、遡及日を設定する場合には注意が必要です。取引の実態や履行状況と矛盾しないか、弁護士・税理士等の確認を取ることが望まれます。
英文契約書の「契約締結日」欄再考
契約書の冒頭や末尾にある「Date:」や「Dated:」の記載について、どのタイミングで記入するか迷うことがあります。
一般的に、英文契約書における「契約締結日(Effective Date)」は、契約条項で明示されている場合にはその日(契約締結日:Effective Date)が優先されます。一方、「署名日(Date of Signature)」は、当事者が実際に署名を行った日を指します。契約書冒頭や末尾に記載される「Dated: April 5, 2025」などの日付は、署名日と一致する場合もありますが、契約効力の発生日とは限りません。
例:
| Dated: April 5, 2025 |
ただし、契約書本文に「This Agreement shall be effective as of April 1, 2025.」とあれば、効力発生日はそれ(April 1, 2025)に従います。こうした場合には、署名日と締結日を混同しないよう、契約実務者が丁寧に書き分けることが求められます。
英文契約書の作成を弁護士に依頼するメリット
英文契約書は、日本語の契約書とは構成や表現、用語の使い方が大きく異なり、特にサインや日付の取り扱いにおいては独特の慣行があります。こうした違いを理解せずに契約書を締結してしまうと、想定外の法的リスクを負う可能性があります。
弁護士に依頼することには、以下のような具体的なメリットがあります。
① 英文契約の慣行や国際商習慣に精通している
たとば、契約書に記載された「shall」「may」「will」などの助動詞の使い分け一つで、義務か任意かが異なる法的効果を生みます。また、「force majeure(不可抗力)」条項や「termination for cause(正当理由による解除)」などは、各国の法律によって解釈が異なるため、英米法に基づいた契約作成が必要です。
署名に関しても、「who has authority(誰が署名権限を持つのか)」を巡って契約の有効性が争われることがあります。これらを見極めるには、英文契約に精通した弁護士の助言が不可欠です。
② 将来的な紛争予防と交渉戦略の構築ができる
たとえば、「署名日をもって契約が発効する」という条項を入れた場合、実際に署名が遅れたらどのような影響があるか、あるいは一方当事者が署名を遅らせて意図的に契約発効を引き延ばすリスクがあるかなど、契約実務に即したリスク分析が可能です。
また、契約の「締結日」が「署名日」と異なる場合に、どちらの当事者がいつから義務を履行すべきか、売買契約であれば代金の支払時期や引渡時期とどう整合させるかといった点でも、条項の設計が重要になります。
③ 記載内容に一貫性を持たせることで有効性を確保
よくある失敗例として、署名欄では「President」と肩書を記載しているのに、契約の定義条項では「代表者」や「執行役員」など別の表現がされているといった、文言の不統一が挙げられます。こうした矛盾は、万が一裁判になった際に不利な解釈を招くなどの問題となるおそれがあります。
弁護士に依頼すれば、契約書全体の整合性をチェックし、不要なリスクを排除できます。また、特定の国の法律を準拠法にする場合(例:This Agreement shall be governed by the laws of England and Wales.)には、その法制度に合わせた構成・表現を取り入れる必要があります。
④ 電子署名やクラウド契約サービスとの併用も相談できる
DocuSignやAdobe Signなどの電子署名サービスの導入が進む中、「この契約類型に電子署名は有効か?」「米国法上での認定署名方法は?」といった実務的な疑問も増えています。これらに対しても、弁護士であれば法的なアドバイスと導入支援をワンストップで提供可能です。
特に契約締結のスピードが求められる取引では、電子署名に対応したテンプレートの整備や運用フローの構築まで含めて、法務体制の強化をサポートできます。
英文契約書のサインおよび日付の書き方のまとめ
以上お読みいただいたように、英文契約書におけるサインおよび日付の取り扱いは、日本語契約とは大きく異なる点が多く、細部にわたって注意が必要です。以下に、本記事のポイントを改めて整理します。
■サインに関する注意点
- 署名欄には「会社名・肩書・署名・名前(印字)」の4項目を明記
- 各ページにイニシャルを求められる場合がある(改ざん防止措置)
- 欧米では印鑑文化がないため、手書き署名が契約の効力発生に直結する
- 肩書や権限の記載が不適切だと、契約の有効性が争点となる可能性もある
■日付に関する注意点
- 契約の効力発生日(Effective Date)と署名日(Date of Signature)を明確に分ける
- 条項中で「遡及日付」を定める場合には実態との整合性が必要
- 「Dated: April 1, 2025」など、文頭や署名欄に日付を記載する箇所が複数存在することがある
- 締結日の記載が抜けていると、契約期間や義務の履行期間に影響することもある
■実務者としての対応のポイント
- 自社での署名権限者の確認(取締役会決議などの必要性も含む)
- 契約書に記載されるすべての氏名や肩書の統一
- 日付が空欄のまま送付されてきた場合は、勝手に記入せず署名者に確認
- 自社側の署名が最後になる場合は、「契約発効日が署名日に依存する条項」に注意
このように、英文契約書におけるサインや日付の書き方は、その一文一文が法的拘束力を持ち、また契約当事者の意図や責任範囲を明確に定める重要な文書です。サインや日付の書き方一つを取っても、軽視すれば大きなトラブルの原因になります。
したがって、英文契約書の作成や締結を検討されている場合には、法律の専門家のアドバイスを受けながら、リスクをチェックし、対応策を盛り込みながら、自社のビジネスが有利に進むよう、準備を進めることが推奨されます。まずは、法律事務所などの無料の問い合わせや資料請求などで、料金や受けられるサービスなど確認し、ご依頼を検討されることをお勧めします。
不明点がある場合は、自己判断せず、専門家のサポートを得ながら具体的な記載方法や法的留意点を理解し、実務に活かすことが極めて重要であり、国際契約トラブルを防ぐ最善の手段といえるでしょう。
▶参考情報:英文契約書の基礎知識については下記の記事でも解説していますので、ご参照ください。
・英文契約書の基礎知識と注意点を解説・サンプル例文付き編

-
弁護士 小野 智博弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士。
慶應義塾大学環境情報学部、青山学院大学法科大学院卒業。企業法務、国際取引、知的財産権、訴訟に関する豊富な実務経験を持つ。日本及び海外の企業を代理して商取引に関する法務サービスを提供している。2008年に弁護士としてユアサハラ法律特許事務所に入所。2012年に米国カリフォルニア州に赴任し、 Yorozu Law Group (San Francisco) 及び Makman and Matz LLP (San Mateo) にて、米国に進出する日本企業へのリーガルサービスを専門として経験を積む。
2014年に帰国。カリフォルニアで得た経験を活かし、日本企業の海外展開支援に本格的に取り組む。2017年に米国カリフォルニア州法人TandemSprint, Inc.の代表取締役に就任し、米国への進出支援を事業化する。2018年に弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所を開設。世界市場で戦う日本企業をビジネスと法律の両面でサポートしている。
-
 採用の際は要注意!雇用契約書で企業が注意すべきポイントとは
事業を行うにあたり従業員を雇用する場合、各従業員と使用者は雇用契約を締結することになります。
雇用契約書の基本知識や雇用契約書と労働条件通知書の違い...
採用の際は要注意!雇用契約書で企業が注意すべきポイントとは
事業を行うにあたり従業員を雇用する場合、各従業員と使用者は雇用契約を締結することになります。
雇用契約書の基本知識や雇用契約書と労働条件通知書の違い...
-
 契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
企業が取引を行う際には、必ず契約書を作成すべきです。
ただしネットなどで出回っている「雛形」「テンプレート」をそのまま使うとリスクが高いので、記名押...
契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
企業が取引を行う際には、必ず契約書を作成すべきです。
ただしネットなどで出回っている「雛形」「テンプレート」をそのまま使うとリスクが高いので、記名押...
-
 賃貸借契約内容に含むべき項目は?書き方のポイントとチェックの重要性
建物や土地、機械などの物を賃貸する場合「賃貸借契約書」を作成しましょう。
契約書がないと有効にならない賃貸借契約もありますし、そうでないケースでも書...
賃貸借契約内容に含むべき項目は?書き方のポイントとチェックの重要性
建物や土地、機械などの物を賃貸する場合「賃貸借契約書」を作成しましょう。
契約書がないと有効にならない賃貸借契約もありますし、そうでないケースでも書...
-
 労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
今回は労働契約と業務委託契約の違いに着目し、特に業務委託契約書に記載すべき重要ポイントを意識しながら、作成時に気を付けておくべき事を解説します。
労...
労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
今回は労働契約と業務委託契約の違いに着目し、特に業務委託契約書に記載すべき重要ポイントを意識しながら、作成時に気を付けておくべき事を解説します。
労...