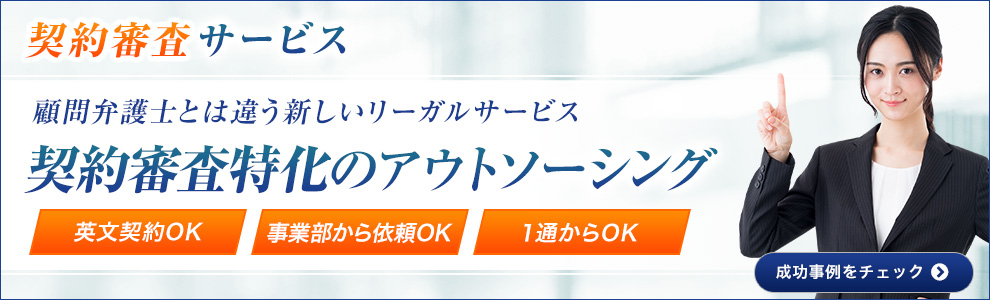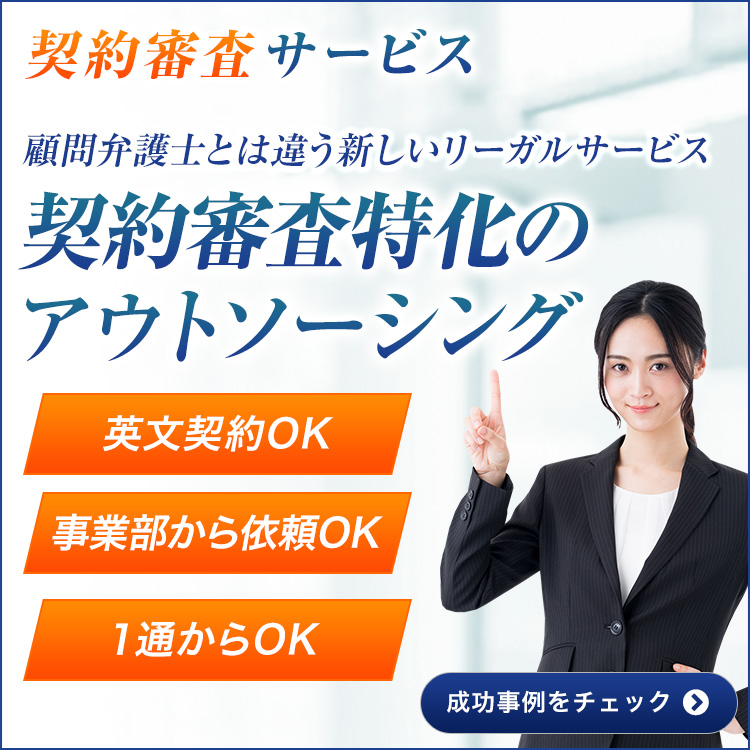- 2025.10.06
「whereas条項」とは?英文契約書の前文を適切に作成するためのガイド|法律事務所が解説
英文契約書の冒頭に、多くの場合で記載されているのが「Whereas」という言葉です。このWhereasという言葉で始まる複数の文を繋げて記載された「Whereas条項」は、形式的な定型文のように見えるかもしれませんが、実は単なる飾りではなく、契約の背景や目的を示す重要な役割を担っています。とりわけ国際取引においては、当事者の立場や契約締結の経緯を整理し、後の契約解釈に影響を与えることも少なくありません。
この記事では、英文契約書を翻訳したり、英語で契約書を作成する際にまず押さえておくべき、「Whereas条項」について、その概要、書き始める前の準備、具体的な作成手順、効率的に作成するためのコツ、作成の際のチェックリスト、その他のポイントを、弁護士が詳しく解説します。
目次
Whereas条項の概要
Whereas条項とは何か?[サンプル例文付き]
Whereas条項とは、英文契約書において冒頭部分に記載される「前文」に相当する条項であり、契約締結の背景や目的を簡潔に示すためのものです。契約本文に入る前に当事者の基本的な立場や意図を整理し、契約の趣旨を明らかにする役割を果たします。
通常、Whereas条項は、「WHEREAS」で始まる複数の文を繋げて記載されます。
例えば、「WHEREAS, Company A is engaged in the business of…; WHEREAS, Company B has approached Company A for…;」のように、事実関係や当事者の目的を列挙していき、最後に「NOW, THEREFORE,…」という文で括り、以下、契約本文に接続していきます。
英米法の下では、一般に、Whereas条項自体に法的拘束力はないとされますが、契約内容が曖昧な場合には、その解釈指針として重要な役割を果たします。また、当事者間で紛争が生じた際に、契約の背景や趣旨を主張する上での根拠となるため、権利義務や賠償額の範囲に影響することもあります。
とりわけ国際取引や技術ライセンス契約など、商流や当事者の関係性が複雑な場合には、Whereas条項によってその背景を明示することが、取引をつつがなく進めるために有益です。
このように、Whereas条項は形式的な前置きに見えるものの、契約の土台をなす重要なパートであるといえます。丁寧かつ正確に作成するよう心がけましょう。
[例文1]
|
CONFIDENTIALITY AGREEMENT This Confidentiality Agreement (the “Agreement”) is made and entered into as of [Date], by and between: [商社Aの正式名称], a corporation duly organized and existing under the laws of [商社Aの所在国/州], with its principal place of business at [商社Aの住所] (“Company A”); and [事業者Bの正式名称], a corporation incorporated under the laws of the State of Delaware, United States, with its principal place of business in the State of California (“Company B”). WHEREAS, Company B is engaged in the business of agricultural machinery and seeks to enhance its technological capabilities; WHEREAS, Company B has approached Company A for consultation regarding potential collaboration or business opportunities, and Company A has agreed to engage in discussions; WHEREAS, in the course of such discussions, both parties anticipate the exchange of certain confidential and proprietary information; NOW, THEREFORE, in consideration of the foregoing and the mutual covenants set forth herein, the parties hereby agree as follows: [以下、本契約条項] |
[例文2]
|
WHEREAS, Buyer desires to purchase from Seller, in accordance with the terms and conditions set forth in this Agreement, certain products manufactured by Seller; and WHEREAS, Seller desires to sell the product to Buyer in accordance with the terms and conditions set forth in this Agreement. NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual agreement herein, the parties hereto agree as follows: |
Whereas条項の法的効力とその影響
英米法の下では、原則として、Whereas条項は法的拘束力は持たないとされています。つまり、Whereas条項に記載された内容そのものが契約当事者に法的な義務を課すわけではなく、それ単体で契約違反の根拠となることは通常ありません。
しかしながら、Whereas条項が全く法的意味を持たないというわけではありません。
例えば、契約書に定める文言が曖昧であったり、当事者間で条項の解釈に争いが生じた場合に、裁判所や仲裁機関はWhereas条項の記載内容を契約解釈の材料として参照することがあります。特に、契約の趣旨や背景に関する記載については、権利義務の範囲など当事者にとって重要な事項に影響する可能性があります。
また、Whereas条項に記載される内容は、契約を締結した際に当事者が認識していた事情でもあるため、後でその記載内容が事実と異なっていたことが判明した場合には、当事者の内心(錯誤の有無や善意悪意など)を推認させる証拠として扱われることもあります。
その他に、Whereas条項の中で、当事者がどのような経緯で契約締結に至ったのか明確にすることで、英米法における契約の有効要件である《約因(consideration)》の存在を推認させる1つの証拠になり得ます。特に、契約本文に明示的な対価や交換条件が十分に記載されていない場合には、Whereas条項が契約の有効性を守ってくれます。
このように、Whereas条項は単なる形式的な導入文ではなく、契約解釈や効力にも一定の影響を及ぼしうる条項であるため、慎重に作成する必要があります。
なお、日本や他の大陸法系の国では、Whereas条項(冒頭文)であっても法的拘束力を持つと解釈される場合もあります。したがって、契約の準拠法を明確にし、当該準拠法における冒頭文の持つ法的意味を明らかにしておくことも極めて重要です。
・英文契約書の基礎知識と注意点を解説・サンプル例文付き編
Whereas条項を書き始める前に確認すべきこと
契約の背景の整理と事実確認
Whereas条項を作成する前には、契約締結の目的や経緯を整理し、それらが取引の実情や当事者の認識と一致しているかを確認する必要があります。誤った背景情報を記載してしまうと、後のトラブルの原因となり、契約全体の解釈にも影響を及ぼしかねません。
例えば、技術ライセンス契約で「既に技術提供が始まっている」と記載してしまうと、未着手であった場合に契約違反と誤解される恐れもあります。事前に関係者との事実確認を行い、認識の相違がない状態で契約書のドラフトに着手することが大切です。
取引と関連する法的要件の理解
Whereas条項は契約の背景や目的を簡潔に示すものですが、その表現には業界や国ごとの法規制を踏まえた慎重な配慮が求められる場面があります。特に国際取引においては、特定の法律や規制に準拠していることを明記することで、法令違反等のリスクを低減できます。
例えば、データ処理契約で「GDPRに準拠する」と記載すれば、欧州当局に対して説明責任を果たしやすくなります。
また、契約相手が後に法令違反を犯した場合でも、Whereas条項に適法性を前提とした文言があれば、当初から加担していなかったことを示す根拠にもなります。
さらに、現場の担当者に法令遵守の必要性を明確に伝える効果や、契約相手に対して自社のコンプライアンス意識の高さを印象づける効果も期待できます。
つまり、適切な理解の下でWhereas条項を記載できると、現地当局からの違反の嫌疑や実際の違反を回避し、また相手方の信頼獲得に繋げることもできるのです。
■具体例①:米国で医薬品の製造委託契約を締結する場合
× 不適切なWhereas条項
| WHEREAS, Company A has developed a new pharmaceutical product that is ready for mass production and sales. |
「新薬の開発が完了し、すぐに販売できる」と明言すると、FDA(米国食品医薬品局)の承認が必要なプロセスを省略しているように見え、契約の規制違反を疑われるおそれがある。
○ 適切なWhereas条項
| WHEREAS, Company A has developed a pharmaceutical product that is undergoing regulatory approval in compliance with the U.S. Food and Drug Administration (FDA) requirements. |
「FDAの規制に準拠して承認手続きを進めている」との表現に変更することで、規制違反の疑いを避けることに繋がる。
■具体例②: EU内の企業とデータ処理に関する契約を結ぶ場合
× 不適切なWhereas条項
| WHEREAS, Company A will process customer data in accordance with the company’s internal privacy policies. |
「自社のプライバシーポリシーに従ってデータを処理する」との記述は、GDPR(一般データ保護規則)の要件を満たしているか不明瞭となり、契約の規制違反を疑われるおそれがある。
○ 適切なWhereas条項
| WHEREAS, Company A and Company B acknowledge that any personal data processing under this Agreement shall comply with the General Data Protection Regulation (GDPR) and applicable national data protection laws. |
GDPRへの準拠を明記することで、規制違反の疑いを避けることに繋がる。また、会社内部(現場)への注意喚起にもなるため、実際にも規制違反を行うリスクを低減できる。
Whereas条項の作成手順
具体的な作成手順(ステップごとに解説)
以下、Whereas条項を作成する際に具体的に何をすればよいかについて、ステップ①~④の順に、明確にお伝えします。
■ステップ①:契約の背景と目的を整理する
まず、契約が締結されるに至った背景や、その目的を正確に整理しましょう。
たとえば、製品の共同開発、技術ライセンスの供与、新規事業の立ち上げなど、契約の動機となったビジネス上の経緯を簡潔に把握し、要点としてまとめる作業が必要です。この過程では、法務担当者のみならず、実務を担当している営業・開発部門などの関係者と協議し、事実関係に齟齬がないよう確認することが肝要です。
また、単に目的だけでなく、過去のやり取りや取引履歴など、前提として共有されている情報があれば、それも含めて整理することで、Whereas条項の記載がより実態に即したものになります。
~ステップ①でのTo Doリスト~
| ◻︎ 契約の起案担当者や営業・開発などの取引関係者にヒアリングを行う。 ◻︎ 契約締結の「きっかけ」「交渉経緯」「目的」を簡潔に要約する。 ◻︎ 曖昧な表現や事実と異なる推測を控える。 |
■ステップ②:当事者の関係性を明確にする
次に、契約当事者の関係性を明確にしましょう。
ここでは、各当事者がどのような立場で本契約に関与するのか、またそれぞれが果たす役割について記載する内容を検討します。
例えば、「A社は製品の製造元であり、B社はその製品を独占的に販売する販売代理店である」といった具合に、立場を端的に記載することで、契約の構造が明確になります。
Whereas条項は契約解釈の指針となるため、当事者の取引関係を正確に記載しておくと、後の紛争時に「当事者がどのような前提のもと契約を結んだのか」を示す証拠の1つとなります。特に多国籍企業間の契約や、複数な委託関係が存在する場合など取引関係が複雑になる場合には、当事者の関与の程度や役割の違いを丁寧に表現することがポイントです。
~ステップ②でのTo Doリスト~
| ◻︎ 各当事者が「売主/買主」「委託者/受託者」「共同開発者」など、どのような立場に立つのかを明確にする。 ◻︎ 相手方の法人格や国籍、登記上の情報も確認し、正式名称で記載する。 ◻︎ 契約本文で登場する当事者名との記載にズレがないかをチェックする。 |
■ステップ③:ドラフトを作成する
ステップ①とステップ②で契約の事実関係を整理できたら、実際にWhereas条項のドラフトを作成してみましょう。
その際には、冗長な表現を避け、簡潔かつ正確な言葉で背景・目的・関係性を記載することが基本です。具体的には、原則として過去または現在の事実を述べる形式(例:「WHEREAS, Company A is engaged in the business of…」)を採用し、権利、義務その他の合意内容など、契約本文に記載すべき事項を混在させないようにしましょう。
また、社内に英文契約のテンプレートがある場合はそれを参考にしつつ、契約ごとの実情に合わせて文言を適宜調整します。他社の契約例や、業界で一般的に使われている表現を参考にするのも有効です。
ただし、表面的な文言の流用に頼るのではなく、各記載事項の意味をしっかりと理解したうえで記載する表現や文言をきちんと選びましょう。
~ステップ③でのTo Doリスト~
| ◻︎ 「WHEREAS, Company A is engaged in…」といった定型句で始める文を1つずつ作成する。 ◻︎ 原則として、事実(現在・過去)の記載に留め、義務・合意は本文に回す。 ◻︎ 社内で使用しているテンプレートがあれば、それをベースに編集する。 ◻︎ 他の契約書や信頼できる文例を参考にする。 ◻︎ 不自然に長い文章や、法律用語の使い過ぎは避ける。 |
■ステップ④:最終確認と修正を行う
最後に、必ず契約全体との整合性をチェックする最終確認を行いましょう。
具体的には、Whereas条項に記載された背景や前提条件が、契約本文と矛盾していないか、記述の重複や不整合がないかを慎重に見直します。
また、記載された内容が取引に係る事実や当事者の認識と一致しているかどうかも確認が必要です。例えば、Whereas条項で「すでに開発が完了している」と記載されているのに、本文では「これから開発を委託する」となっていれば、明らかな齟齬が生じ、後のトラブルの原因になります。
さらに、準拠法によってWhereas条項の法的な意味合いが変わってき得るので、その点も考慮に入れつつ、抜け落ちや修正すべき点がないかを確認しましょう。
最後に、誤字脱字や名称の誤り等、読んだ際に不自然な印象を受ける点がないかをきちんと見直しましょう。
~ステップ④でのTo Doリスト~
| ◻︎ 契約本文に記載された内容と、Whereas条項の文言が矛盾していないかチェックする。 ◻︎ 前文で記載した内容が、当事者双方で事実として認識されているか確認する。 ◻︎ 必要に応じて、社内の法務部門または外部弁護士によるレビューを依頼する。 ◻︎ 契約の準拠法(例:日本法、米国法など)に応じて、前文の効力や位置づけも考慮する。 ◻︎ 誤字脱字や名称の誤り、主語の省略など、形式面も丁寧に見直す。 |
専門家によるレビューを受けることも有用
Whereas条項について適切なチェックを行うには、当該契約の準拠法を踏まえ、法的拘束力の有無や、個別の取引上記載しておくべき事項、その他争訟上の原則(表現による禁反言等)を判断する必要があります。
そのため、契約の準拠法に精通した専門の法律事務所によるレビューを受けることは、契約全体の信頼性と交渉力を高めるうえで、実務上非常に有効な手段です。
当事務所では、英文契約の背景事情やビジネスモデルを踏まえた上で、Whereas条項の文言チェックや調整案のご提案を行っており、企業の皆様の実務上の法的リスクを未然に防ぐお手伝いをいたします。
Whereas条項を効率的に作成するコツ
以下では、Whereas条項を効率的かつできる限り正確に作成するため、押さえておくべき3つのポイントを解説します。
(1)テンプレートの活用
Whereas条項の作成にあたっては、過去の契約書や社内の定型文例(テンプレート)を積極的に活用することが効果的です。業種や契約類型ごとに一定の表現パターンが確立していることが多く、それらを参考にすることで、無駄な検討時間を省きつつ、表現ミスや抜け漏れのリスクを低減できます。
ただし、文例をそのまま流用するのではなく、当該契約の目的や背景に照らして内容を調整することが重要です。テンプレートはあくまで「たたき台」であるという意識を持ち、自社の実情に合った修正を加えるようにしましょう。
(2)契約全体との整合性を意識する
Whereas条項は契約本文に先立つ導入部分ですが、そこに記載された内容が本文と食い違っていれば、契約全体の信頼性を損なうおそれがあります。
例えば、Whereas条項で「すでにシステム開発が完了している」と記載しつつ、本文では「開発をこれから委託する」となっていれば、内容の矛盾によって解釈の混乱が生じかねません。背景説明に過ぎないとはいえ、Whereas条項は解釈の補助資料として重視される場面もあるため、契約本文と一貫性が保たれているか、必ず最終チェックを行いましょう。
(3)社内での情報共有を徹底する
Whereas条項に記載すべき背景情報は、法務部門だけでなく営業、技術、経営陣など、複数部門にまたがる内容を含むことがあります。そのため、条項作成にあたっては社内での情報共有を丁寧に行い、実態と齟齬のない内容とすることが重要です。
また、専門的な法的判断が必要な場面では、外部の法律事務所と連携してレビューを受けることも有効です。
Whereas条項を成功させるためのチェックリスト
✅ 記載内容が正確か?
契約締結の背景、当事者の事業内容、契約目的などが事実と一致しているか確認しましょう。
特に「~している(is engaged in)」などの現在形表現を用いる際には、現在の取引状況とズレには注意が必要です。
また、「優れた技術力を有する」といった主観的・評価的な表現はなるべく避けて、「一定の分野における特許を保有している」といった客観的事実に基づいた記述を行うように心がけましょう。
✅ 契約本文と矛盾していないか?
Whereas条項に記載された内容が、契約本文中に定める権利義務の内容と食い違っていないかを照合しましょう。
✅ 法的リスクがないか?
当該契約の準拠法(例:日本法、英米法)や適用される現地法令を踏まえたうえで、Whereas条項の文言が適切なものとなっているか、また不利に解釈されるリスクがないかを検討しましょう。
✅ 社内外で認識が共有されているか?
Whereas条項の内容について、社内や相手方との間で誤解なく共有されているかを確認しましょう。内部や外部で認識が異なると、トラブルの元になるため注意が必要です。
Whereas条項のまとめ
Whereas条項は契約の冒頭に記載される形式的な導入文に見えますが、その実、契約の背景・目的・当事者の関係性を明確にする重要な役割を担っています。記載内容が不正確であったり、契約本文と矛盾する表現を用いれば、条項や文言の解釈が争われた際に自社に不利に働く可能性もあるため、正確性と整合性が求められます。そのため、社内外との情報共有を徹底し、専門家と連携しながら慎重に文案を検討する姿勢が不可欠です。
また、Whereas条項に関する実務の精度を高めるには、継続的な学習が大切です。英米法における契約解釈の考え方や、表示による禁反言などの法的概念に関する理解を深めておくことで、記載内容が実務に即したものとなります。
さらに、近年は業界や国ごとの規制の変化が激しく、AI・個人情報・サステナビリティといった新たな分野では適用される関係法令の内容や法改正のポイントなど、最新動向の把握が求められます。
Whereas条項は小さなパートですが、契約全体の「語り出し」として、信頼性や交渉力を高めるカギを握る存在です。形式的な作業で済ませず、戦略的に活用する意識を持つことが、実務上の差を生む第一歩となります。
Whereas条項はじめ、英文契約書は、弁護士などの専門家に適切なアドバイスを受けながら作成されることをお勧めします。

-
弁護士 小野 智博弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士。
慶應義塾大学環境情報学部、青山学院大学法科大学院卒業。企業法務、国際取引、知的財産権、訴訟に関する豊富な実務経験を持つ。日本及び海外の企業を代理して商取引に関する法務サービスを提供している。2008年に弁護士としてユアサハラ法律特許事務所に入所。2012年に米国カリフォルニア州に赴任し、 Yorozu Law Group (San Francisco) 及び Makman and Matz LLP (San Mateo) にて、米国に進出する日本企業へのリーガルサービスを専門として経験を積む。
2014年に帰国。カリフォルニアで得た経験を活かし、日本企業の海外展開支援に本格的に取り組む。2017年に米国カリフォルニア州法人TandemSprint, Inc.の代表取締役に就任し、米国への進出支援を事業化する。2018年に弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所を開設。世界市場で戦う日本企業をビジネスと法律の両面でサポートしている。
-
 採用の際は要注意!雇用契約書で企業が注意すべきポイントとは
事業を行うにあたり従業員を雇用する場合、各従業員と使用者は雇用契約を締結することになります。
雇用契約書の基本知識や雇用契約書と労働条件通知書の違い...
採用の際は要注意!雇用契約書で企業が注意すべきポイントとは
事業を行うにあたり従業員を雇用する場合、各従業員と使用者は雇用契約を締結することになります。
雇用契約書の基本知識や雇用契約書と労働条件通知書の違い...
-
 契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
企業が取引を行う際には、必ず契約書を作成すべきです。
ただしネットなどで出回っている「雛形」「テンプレート」をそのまま使うとリスクが高いので、記名押...
契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
企業が取引を行う際には、必ず契約書を作成すべきです。
ただしネットなどで出回っている「雛形」「テンプレート」をそのまま使うとリスクが高いので、記名押...
-
 賃貸借契約内容に含むべき項目は?書き方のポイントとチェックの重要性
建物や土地、機械などの物を賃貸する場合「賃貸借契約書」を作成しましょう。
契約書がないと有効にならない賃貸借契約もありますし、そうでないケースでも書...
賃貸借契約内容に含むべき項目は?書き方のポイントとチェックの重要性
建物や土地、機械などの物を賃貸する場合「賃貸借契約書」を作成しましょう。
契約書がないと有効にならない賃貸借契約もありますし、そうでないケースでも書...
-
 労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
今回は労働契約と業務委託契約の違いに着目し、特に業務委託契約書に記載すべき重要ポイントを意識しながら、作成時に気を付けておくべき事を解説します。
労...
労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
今回は労働契約と業務委託契約の違いに着目し、特に業務委託契約書に記載すべき重要ポイントを意識しながら、作成時に気を付けておくべき事を解説します。
労...