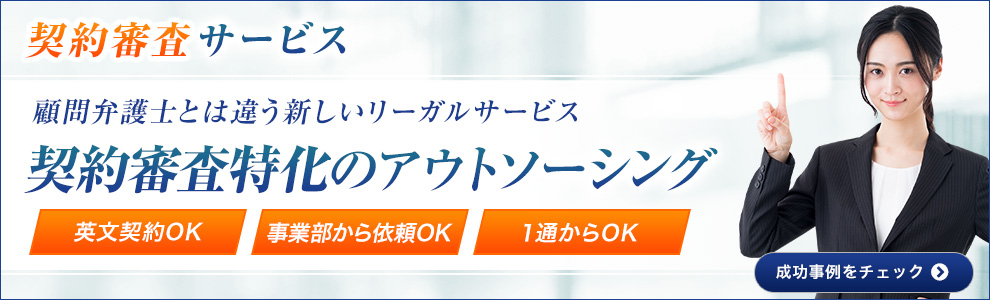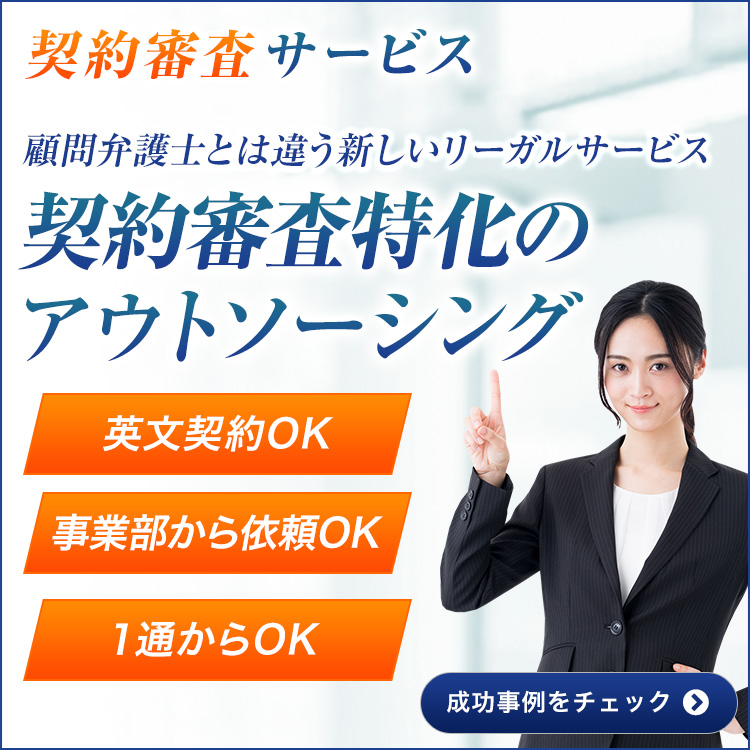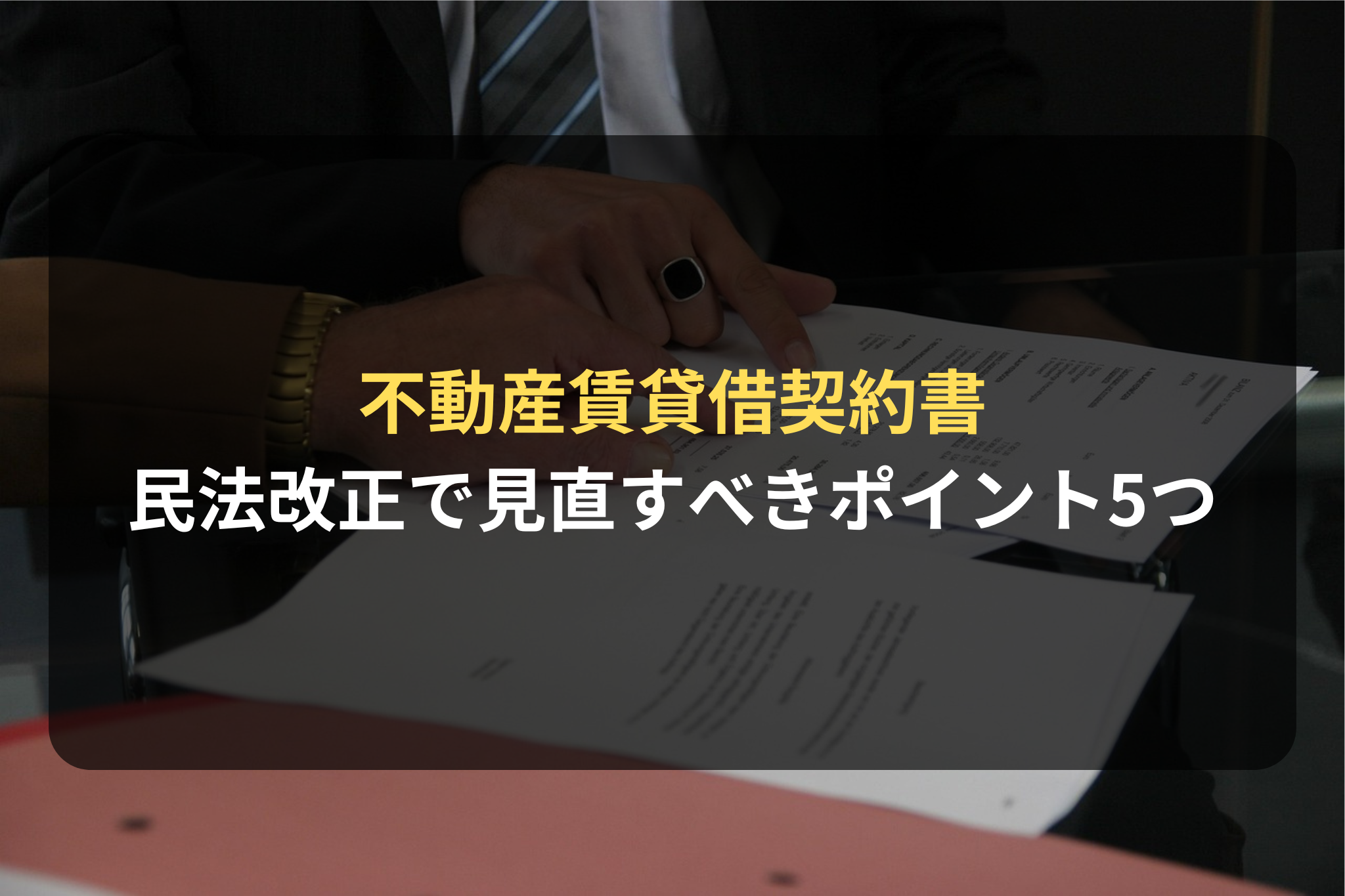
- 2025.04.09
不動産賃貸借契約書の見直しはお済みですか?民法改正(債権法改正)への対応のポイントをわかりやすく解説
2020年4月1日に改正民法が施行され、不動産業界にも大きな影響がありました。不動産賃貸に携わる事業者の方は、自社の不動産賃貸借契約書の民法改正対応はお済みでしょうか?民法改正に対応せず、従来の契約内容のままにしておくと、契約条項が無効になる可能性がありますので注意が必要です。
この記事では、不動産賃貸に関わる事業者の方々に、ぜひ知っておいていただきたい民法の主な改正事項、不動産賃貸実務への影響及び不動産賃貸借契約書の見直しポイントと見直しの方法について、わかりやすく解説します。
目次
主な改正事項と不動産賃貸実務への影響
不動産賃貸借分野における民法改正は、契約当事者間の権利と義務のバランスをより公平に保つこと、及び不動産賃貸市場の透明性を高めることを目的としています。例えば、敷金返還や原状回復のルールが明確化され、賃貸借契約終了時の不動産の返却に関するトラブルを軽減し、紛争解決の手引きを提供しています。
また、連帯保証人に関しては、契約締結時に極度額の設定が義務付けられ、これにより保証人の負担リスクが明確にされました。更に、賃貸人や管理会社は、賃借人から連帯保証人への情報提供義務や、連帯保証人からの問い合わせに対する回答義務が新設されたことに対応する必要があります。
これらの変更により、賃貸の管理会社や賃貸物件のオーナーは、改正民法の要件を満たすため、契約書の内容の再検討や更新を行わなければならなくなり、新たな説明事項や対応事項が従来の実務に追加されることになりました。
改正民法の適用時期
民法改正への対応を行うにあたり、まずは、締結された賃貸借契約は、旧民法が適用されるのか、改正民法が適用されるのかを確認しましょう。契約に関する法の適用は、契約締結時点が基準となるため、原則として改正民法の施行前の契約は旧民法が引き続き適用され、2020年4月以降に締結した新規の契約、更新を行うものは改正民法の適用となります。ただし、当事者としては、更新後は改正民法が適用されるとは知らなかった、または適用されるのは改正民法か旧民法か等の疑義が生じる場合もあるかもしれません。契約の相手方と協議の上、いずれが適用されるのかを確認し、契約書に追記する、または覚書を交わしておくなどして、改正民法の適用時期を巡るトラブルを回避することが望ましいでしょう。
契約内容の見直しポイント5点
今回の改正による変更点の中でも、特に注意して確認するべき5つのポイントを挙げていきます。
連帯保証人への情報提供義務の新設
改正民法第465条の10は、事業用物件の不動産賃貸借契約で連帯保証人をつける場合は、賃借人から連帯保証人に、賃借人の財産状況等を情報提供することを義務付けました。これは、連帯保証人の候補者が、連帯保証人となることを検討する際、賃借人にどの程度の財産があるかを把握する機会を与え、連帯保証人が想定外及び多額の保証債務の履行を求められないようにするためです。
賃借人は、①賃借人の財産及び収支の状況、②賃借人が賃貸借契約の他に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況、③賃借人が賃貸人に保証金などの担保を提供するときは、その旨及びその内容についての情報を連帯保証人に提供する必要があります。
また、賃借人が連帯保証人に対して情報提供義務を果たしていないことについて知っている、または知らないことについて賃貸人に過失があった場合は、連帯保証人は連帯保証契約を取り消すことができます。
敷金返還についてのルールの明確化
改正民法は、敷金について次のように規定しています(第622条の2第1項)。
「賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。」
敷金とは、賃貸借に基づいて賃借人が負う金銭債務を担保するために、賃借人が賃貸人に交付する金銭のことです。改正民法では、賃貸人は、賃貸借契約が終了して明け渡しを受けた時点で、敷金返還債務が生じること、及びその額は受領した敷金の額から、それまでに生じた金銭債務の額を差し引いたものであることが明記されました。
原状回復についてのルールの明確化
改正民法は、原状回復義務について次のように規定しています(第621条)。
「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」
改正民法では、賃借人は通常損耗(通常の使用によって生じた傷みや経年劣化)に関しては原状回復義務を負わないことが明記されました。
前項の敷金返還や、原状回復義務については、民法改正前の判例や実務の実情を反映したものであり、これまでの実務におけるルールを変更するものではありませんが、旧民法の文言上では曖昧であった点を明確にしたということになります。
連帯保証人についての極度額設定の義務化
連帯保証人が結ぶ連帯保証契約は、いわゆる「根保証契約(一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約)」と呼ばれ、旧民法においては、保証人となる時点では将来どれだけの金額の債務を保証しなければならないのかが分からないという性質がありました。
改正民法第465条の2は、個人(保証人が法人ではないもの)の根保証契約について、保証人は極度額を限度として、その履行をする責任を負い(第465条の2第1項)、極度額(保証人が支払義務を負う限度額のこと)を定めなければ、その効力を生じない(第465条の2第2項)と定めました。
これにより、連帯保証人が保証する極度額の設定が義務付けられ、極度額を超える債務は、保証責任を負わないこととなりました。また、不動産賃貸借契約において連帯保証人を付けるときは、必ず、契約締結の時点で極度額を書面または電磁的記録上で定めなければ無効とされます(民法第465条の2第3項で、同第446条第2項及び第3項を準用)。
連帯保証人からの請求に対する回答義務の新設
改正民法第458条の2として、賃貸人は連帯保証人から請求を受けた場合、賃借人による家賃の支払状況等について遅滞なく回答することが義務付けられました。回答を怠ると、例えば、賃借人が家賃を滞納し、賃貸人から連帯保証人に滞納家賃の支払いを請求しなければならなくなった場合に、連帯保証人から回答義務違反を指摘され、請求に支障が生じることが考えられます。不動産賃貸に携わる事業者の方は、連帯保証人からの問い合わせに誠実に対応するよう徹底する必要があります。
| ▶参考情報:賃貸借契約については下記の記事でも解説していますので、ご参照ください。 ・賃貸借契約内容に含むべき項目は?書き方のポイントとチェックの重要性 |
不動産賃貸借契約書の見直し方法
最後に、契約書見直しのプロセスを確認していきましょう。
契約内容の確認と、修正または追加する条項の精査
まず、現行の契約書を精査し、改正点に照らして適切でない条項や抜けている条項がないか確認することが大切です。敷金返還や原状回復のルール明確化、連帯保証人に関する新ルールなど、本コラムで解説した項目に特に注目してください。契約内容を確認した後は、改正民法に対応していない条項を修正または追加する必要があります。例えば、連帯保証人の極度額設定の義務化に関して、これまでに設けられていなかった場合、新たにその条項を追加しなければなりません。変更を加えたことによって、他の条項に影響がないか、確認することも必要です。
当事者間の合意形成および変更後の契約書等の作成
変更する契約内容が決定したら、次に変更手続きへと移ります。変更手続きでは、まず賃貸人と賃借人との間で変更内容についての合意形成を図ります。その上で、覚書や変更契約書などの正式な書類を作成し、双方が記名押印(または署名捺印)することが一般的です。契約書作成の過程では、法的な知見を持つ専門家の助言を受けることが望ましいでしょう。
なお、契約変更の際には、連帯保証人に対しても変更内容の通知や必要に応じた同意を得る作業が生じることがあります。例えば、事業用物件の賃貸借における情報提供については、賃貸借契約書に必要な事項について記載した後、連帯保証人がその内容を確認し、十分理解した上で契約を交わすことで、賃借人は情報提供義務を果たすことができるでしょう。また、賃貸借契約の更新の際、保証契約も合意更新する場合や、新たな保証契約を締結する場合には、極度額の設定が必要となります。更新時に連帯保証人に連絡を取らず、確認をしない等のあいまいな手続きは、トラブルの原因となりかねません。合意更新をする際は、きちんと連帯保証人にも連絡し、保証の意思を確認するとともに、合意した額を極度額として設定しましょう。さらに、賃借人の債務の履行状況に関する保証人への情報提供については、「言った言わない」のトラブルに発展しないよう、書面又は電子メール等の電磁的記録によって行う旨を定めておくとよいでしょう。
このようなプロセスを通じて、民法改正に対応した賃貸借契約書を作成することができます。変更後の契約内容は、その後の賃貸実務において重要な基盤となりますので、変更内容を正確に理解し、実務に適切に反映することが大切です。
不動産賃貸借契約書の見直しのまとめ
改正民法は、2020年4月1日より施行され、不動産賃貸分野にも大きな影響がありました。この改正は、不動産賃貸に携わる事業者の方に、契約内容の見直しや運用面における慎重な対応を求めています。
民法改正の背景には、社会の変化とニーズに応じて、より公平で現代的な法律の下、契約関係が築かれることを目指すという考え方があります。これを踏まえ、不動産賃貸借契約における連帯保証人に対する義務、敷金や原状回復費用の取り扱いなど、実務において、具体的な対応を行うことが求められています。さらに詳しい情報や自社の場合はどうなるのか等、不明点や疑問点が出てきた場合は、法律専門家に相談することをお勧めします。

-
弁護士 小野 智博弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士。
慶應義塾大学環境情報学部、青山学院大学法科大学院卒業。企業法務、国際取引、知的財産権、訴訟に関する豊富な実務経験を持つ。日本及び海外の企業を代理して商取引に関する法務サービスを提供している。2008年に弁護士としてユアサハラ法律特許事務所に入所。2012年に米国カリフォルニア州に赴任し、 Yorozu Law Group (San Francisco) 及び Makman and Matz LLP (San Mateo) にて、米国に進出する日本企業へのリーガルサービスを専門として経験を積む。
2014年に帰国。カリフォルニアで得た経験を活かし、日本企業の海外展開支援に本格的に取り組む。2017年に米国カリフォルニア州法人TandemSprint, Inc.の代表取締役に就任し、米国への進出支援を事業化する。2018年に弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所を開設。世界市場で戦う日本企業をビジネスと法律の両面でサポートしている。
-
 採用の際は要注意!雇用契約書で企業が注意すべきポイントとは
事業を行うにあたり従業員を雇用する場合、各従業員と使用者は雇用契約を締結することになります。
雇用契約書の基本知識や雇用契約書と労働条件通知書の違い...
採用の際は要注意!雇用契約書で企業が注意すべきポイントとは
事業を行うにあたり従業員を雇用する場合、各従業員と使用者は雇用契約を締結することになります。
雇用契約書の基本知識や雇用契約書と労働条件通知書の違い...
-
 契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
企業が取引を行う際には、必ず契約書を作成すべきです。
ただしネットなどで出回っている「雛形」「テンプレート」をそのまま使うとリスクが高いので、記名押...
契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
企業が取引を行う際には、必ず契約書を作成すべきです。
ただしネットなどで出回っている「雛形」「テンプレート」をそのまま使うとリスクが高いので、記名押...
-
 賃貸借契約内容に含むべき項目は?書き方のポイントとチェックの重要性
建物や土地、機械などの物を賃貸する場合「賃貸借契約書」を作成しましょう。
契約書がないと有効にならない賃貸借契約もありますし、そうでないケースでも書...
賃貸借契約内容に含むべき項目は?書き方のポイントとチェックの重要性
建物や土地、機械などの物を賃貸する場合「賃貸借契約書」を作成しましょう。
契約書がないと有効にならない賃貸借契約もありますし、そうでないケースでも書...
-
 労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
今回は労働契約と業務委託契約の違いに着目し、特に業務委託契約書に記載すべき重要ポイントを意識しながら、作成時に気を付けておくべき事を解説します。
労...
労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
今回は労働契約と業務委託契約の違いに着目し、特に業務委託契約書に記載すべき重要ポイントを意識しながら、作成時に気を付けておくべき事を解説します。
労...